「金って積み立てる意味あるの?」「どのくらい儲かるの?」「NISA非対応だし損しない?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
僕自身、SBI証券で純金積立を2022年から始めて約3年。
今回はそのリアルな損益と評価額を公開しながら、「金積立は続ける価値があるのか?」「ETFとの違いは?」を整理してお届けします。
1. 金積立を始めたきっかけ|インフレと為替への漠然とした不安
2022年当時、世の中はインフレと円安でざわついていました。
- 日用品や光熱費の値上げ
- アメリカの利上げ → 円安進行
- 株や不動産がすでに高くなっていて買いづらい…
そんな中、「金(ゴールド)はインフレや有事に強い」「世界共通の価値がある」といったワードをよく目にするようになり、気になり始めました。
調べてみると、金は以下のような特徴があることがわかりました。
- 供給量が限られている
- 世界中で通用する資産
- 株や債券と違い、無配当で価格のみで評価される
「何か起きたときに備えて、金をコツコツ持っておくのは悪くないかも…」
そんな気持ちから始めたのがきっかけです。
2. ETFではなく「純金積立」を選んだ理由
金投資には大きく分けて、以下のような手段があります:
| 投資手段 | 内容 | コスト | 売却のしやすさ | 積立のしやすさ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純金積立 | 毎月一定額で金を購入(現物保有) | 買付手数料あり | △(口座内売却) | ◎ | 少額から始めやすい |
| 金ETF(国内) | 株式のように証券口座で取引 | 低コスト | ◎(市場売却) | △(積立対応限定) | 価格連動型・コスト効率が高い |
| 金ETF(米国) | GLDなど | 為替リスクあり | ◎ | △ | 世界的に人気・分配金なし |
| 金地金 | 実物の金を購入 | 高コスト(スプレッドあり) | △ | × | 自宅保管可能・現物としての安心感 |
「コスト面ではETFが有利」と言われているため、最初はETFで積み立てようと思っていました。
でも、2022年当時のSBI証券では、国内株(=金ETF)を定額で自動積み立てする仕組みがなかったんです(※2024年8月から「日株積立」としてスタート)。
米国株ETFなら積立OKだったんですが、資産をまとめて管理したかったので見送りました。
もちろん、ETFの方が信託報酬が安く、NISA対応で税制メリットもあります。
でも僕は、
- 長期前提で頻繁に売買しない
- NISA枠はすでに他の用途で埋まっていた
- 現物として積み立てている感覚が面白そうだった
という理由から、あえて純金積立を選びました。
3. 実際に3年積み立てた結果と評価額・損益を公開!
| 年 | 種別 | お預かり重量(g) | 評価損益(円) | 金額(評価額) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金 | 7.6548 | -1,371 | 58,598 |
| 2023 | 金 | 19.0389 | 18,571 | 178,395 |
| 2024 | 金 | 29.3317 | 109,465 | 389,056 |
| 2025 | 金 | 32.7491 | 171,366 | 500,865(2025年6月30日時点) |
- 2022年9月:スポット購入(3万円)
- 2022年10月〜:月1万円の積立
- 2025年6月:積立反映なし(設定ミス)
3年間で積み立てた金額は【329,499円】、
2025年6月末時点の評価額は【500,865円】、
つまり**+171,366円の含み益**が出ています。
世界情勢から来る金価格の高騰の影響もありますが、正直こんなに評価益が出るとは思ってませんでした(笑)。金の価格も、現時点で約1万5千円と一体どこまで上がるのか、といった状態です。
4. 金積立のメリットとデメリット
メリット
- ✅ インフレや有事(戦争・金融不安)に強い
- ✅ 長期で見ればリスク分散になる
- ✅ 少額(1,000円〜)でも始めやすい
- ✅ 自動積立で習慣化しやすい
- ✅ 見た目上プラスになっていると嬉しい(笑)
デメリット
- ⚠️ 買付手数料が高い(SBI証券は1.65%)
- ⚠️ NISA非対応で売却益は課税対象
- ⚠️ 配当や利息がない
- ⚠️ 価格変動リスクもそれなりにある
金は価格が上下する商品ですし、全力投資すべき資産ではありません。
ただ、少額でインフレ対策や守りの資産として持っておくのはアリだと感じています。
5. 今後の方針|純金積立は継続。ETF併用も検討中
積立3年の今、純金積立を「今さら売るのもったいない」と感じています。
売却すれば当然税金がかかるし、ここまで積み上げたものをゼロにする気にはなれません。
なので、純金積立はこのまま継続。
一方で、ETF積立も今後は併用するかもしれません。
ETFなら信託報酬も安く、NISAで非課税運用もできる。
目的別に「現物金積立」と「ETF積立」を使い分けることで、バランスの取れた金投資になると思います。
金積立に向いている人・向いていない人
向いている人
- インフレや円安が心配な人
- 現物資産を少し持っておきたい人
- 長期でコツコツ投資したい人
- NISA枠がすでに埋まっている人
向いていない人
- 配当や利回りを重視する人
- 短期での利益を狙う人
- 手数料を極端に気にする人
- NISAで全資産を運用したい人
まとめ|金積立は「目的と期待値」を間違えなければアリ!
金積立は、大きな利益を狙うというよりも「守りの資産」として持つイメージが大切です。
- インフレ・円安・有事リスクへの備え
- 長期で見れば値上がり益のチャンスもある
- 株や債券と異なる値動きをするため、分散効果がある
そういった観点から、僕はこれからも純金積立を継続しつつ、ETFでの積立も選択肢に入れていくつもりです。


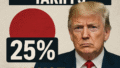
コメント